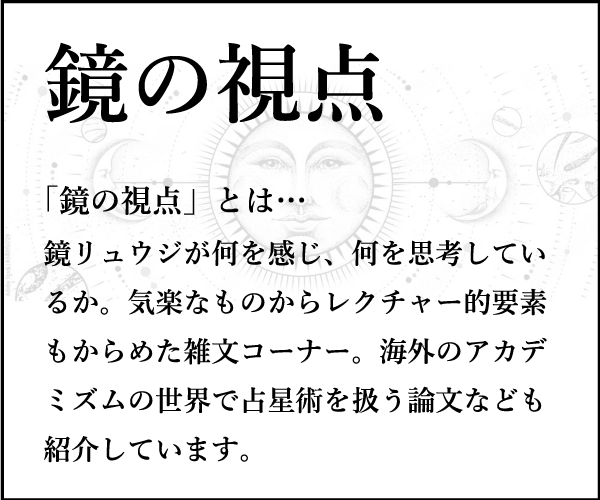「占い」を看板に掲げるようになってからずいぶん経つ。16歳で雑誌デビューしてから今にいたるのだから今年でもう35年か。生涯の仕事にするつもりなど毛頭なかったから、運命とは理解しがたく不思議なものだと“占い”が専門の僕が言うのも変だろうか。
ともあれその35年の間、変わらず投げかけられ続けてきた言葉がある。それは「女性は占いが好きですよねえ」という一言だ。
そのありきたりな、あるいは無邪気な一言の響きに、僕はこれまで戸惑ってきたし、もう少し正直に言えば少しばかり傷つきもしてきた。
「女性は占いが好きですよねえ」これは事実だ。
僕はいわゆる個人鑑定はしたことがなく、雑誌やWEBなどのメディアでしか仕事をしていないが、だからこそより大きなデータを持っていると言える。その中で、少なくとも僕の読者の8割は女性だ。同じことは英国でも言えそうで、これは洋の東西を問わない。女性に人気の商売をしていて、おかげさまで長年、望む以上の女性ファンがいてくださってありがたいことこの上ない。
けれど、「女性は占いが好きですよねえ」という素朴な言葉に潜む軽い侮蔑の響きを僕は聞き流すことができない。そして相当鍛えられ毛も生えたはずの心臓が、その言葉にチクリとした痛みを感じてしまうのである。
なぜ女性は占いが好きなのか。素朴な答えとしては女性は生得的に感受性が強く、自然のサイクルに敏感で、もしかしたら霊的繊細さを兼ね備えているからだ、というものがある。いわゆる「女性原理」を前提とするものだ。しかしこうした考えそのものが「強い」男性が生み出した女性への抑圧的志向の産物にすぎないとは、多くのフェミニズム理論が批判してきたことである。
もう少しお利口そうな回答は、こうだ。歴史的には占星術をはじめ占いは社会の基幹部分にあったが、近代化=合理化によって少なくともタテマエとしては社会を動かすのは合理的に自己決定できる人間であるはずだとされた。そして一昔前まではそれは「成人男子」だったわけで、占いのような「非合理」な営みは「オンナコドモ」だけに許容されるようになったのだ――。これはかなり説得力があるが、しかし、占いの現場に立つ身としてはこういう抽象的な理屈だけで人が動いているとは実感できない。
ただ、こうした説明を聞いたとしても「女性ってやっぱり占いなんて非合理的なものに頼っているおバカでカワイイ存在なんですよねえ、あなたもそういう商売をなさって」という響きを僕が感じてしまうのはあながち被害妄想とは言えまい。
僕自身、なぜ女性が占い好きなのか、答えはわからない。時代や地域によってもかわるだろうし、これは普通に思われているよりはるかにデリケートな問題である。
だが、今回、僕は一つの「答え」を得た気がする。しかも、理論ではなく物語のかたちで。
そう、それが木内昇の短編集『占』である。
占いや霊感を一種のレンズとしてさまざまな生き方をする女性たちの心模様を鮮やかに描き出してゆくこの作品は、占いが引き起こす人生の変転のみならず、占いを前にした時の(時に占いをする側の)心の動きを見事に解析している。それは実に多様である。恋人の本心を知りたい翻訳家。家庭の平穏さを誇りたい主婦。従業員の扱いに悩む経営者――。それぞれの切実な葛藤や欲望が占いによって炙り出されていて、これを読むと「女性は占いが好き」などと女性を一括りにしてしまうのがいかに乱暴かがわかる。各短編の登場人物の人生は交差してゆくのだが、それぞれの女性から見た人生の風景のいかに個性豊かなことか。
そして、少し生意気なことを言わせていただければ時代背景を大正末期から昭和への時代にされたことの見事さに舌を巻いた。この設定が登場人物たちのセリフに独特の品や味を加えることを可能にしていることももちろんある。しかし、それ以上に、女性たちが急速に「自由」を手にしていく一方で、従来の男尊女卑的な因習の重力を強く感じているこの時代は、見方によっては令和のこの時代そのものを映し出しているように見える。これは「時代小説」ではない。「今」の物語でもある。
占い好きとして一言付け加えれば西洋占星術やタロットが輸入されはじめるのも実はこの大正期である。少し時代は先行するが英国ではヴィクトリア朝末期に「女性霊媒」たちが台頭した。続編があるとすればぜひこうした西洋の占いも入れていただきたいのだけれど……。
ともあれ、これは本当に僕にはありがたい作品である。もし次回、「女性は占いが好きですよねえ」の一言に傷ついたら、この『占』を勧めてやればよいのだから。相手が何かを感じ取ってくれれば我が意を得たり。そしてもし鈍感にすぎてこちらの意図が伝わらなくても損はない。
なぜならこれは小説として最高に面白いのだから、相手にも損はない。そう、占い師とはこれくらいしたたかなのである。
初出:新潮社『波』2020年2月号