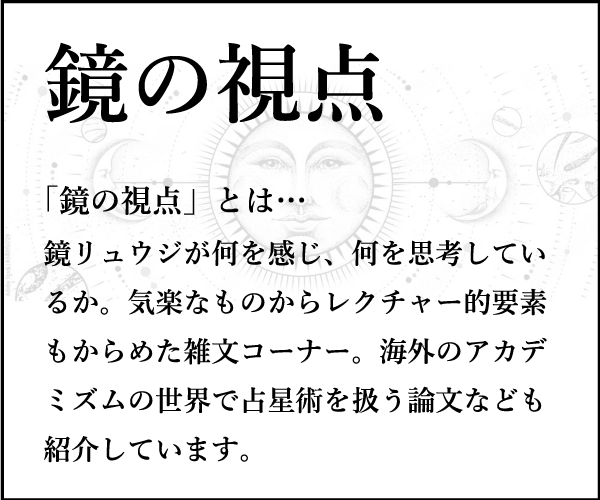●「時」という概念のはじまり
ついさきごろ、毎年出させていただいているダイアリー、「Sun and Moon Diary」の2012年版を校了したところだ。
本来、活字の出版物には間違いがあってはならないのだが、魚座で月が牡羊座にあるぼくはどうしてもるーズで、ついつい、ザルになってしまう。ミスがいろいろあって、あとで後悔することが多いのだが、こと手帳や暦の場合には、そういうわけにはいかない。日付の間違いがあってはいけないのだから、いつも以上に神経を遣う。
出版はちょっと気が早くて9月。だから、お盆のころ、夏の暑いさかりにスタッフや編集のみなさんと膝を突き合わせては相互チェックをする、というのがここ数年の恒例行事になっている。
冷たい麦茶をごくごく飲みながら、細かい星の動きの文字を読みあげ、追いかけるのがぼくたちの夏の風物詩となっている、というわけである。
これはこれで結構大変なのだが、しかし、これが百年、百五十年前だったらどうだろう。
太陽や月の動きを追いかけ、日食や月食を予測し、そして星の運行と日付や季節を合致させるのは至難の技であった。それは地道な観測と、明晰な数学的才能の希有な結婚によってのみ可能なことだった。
いまでは、すぐれた望遠鏡などによる観測技術も、コンピュータによる精緻な計算によって月の満ち欠けや食の時間はそれこそ秒単位で天文台によって発表されている。ぼくたちはそれを利用させていただくことができる。けれど、わずか百年前にはそんなリソースは期待すべくもなかった。そして江戸のころ、近代化に向けて日本人はその才能のすべてをかけて暦という難問にチャレンジしてきたのだった。
江戸の改暦にかかんにチャレンジした渋川春海の活躍を描いた青春小説『天地明察』(冲方丁著 角川書店)は、そのエピソードをよく伝えている。ほんと、スカッとする小説なので、ぜひ読んでいただきたい。学術書じゃないので史実そのものではないかもしれないけれど、暦を作るということがどんなことだったのか、イメージはきっとつかめると思う。
それにしても近代になってからの作暦がこんなに大変だったことを考えれば、人類の文明の発祥のときの暦の作成がどんなに大変だったか、想像に難くない。
そもそも、日が沈んだ時、必ずもう一度太陽が昇って新しい1日が始まるという事実を初めて発見した人のいかに偉大であったことか。厳しい冬のあと、数カ月で春が来ることを知った人のいかに天才であったことか。
それは「時」という概念の始まりでもあり、生命の有限性の発見でもあっただろうし、共同体の人々が生活を律し、計画的に社会組織を運営し始めたこととまさに同義だったはずだ。
よく、天体観測による暦の作成といえばバビロニア文明だとか中国の黄河文明といったところに起源が求められる。それは文字による天文観測の記録が残っているだけのことであって、それ以前の「文明」にも天体のリズムを観測していた証拠はある。
文字がなくてもストーンヘンジをはじめとした巨石文明をつくった人々は、ストーンサークルを天体の運行と一致させて建築していた証拠がある。
それどころか、紀元前2万5千年ごろ、考古学者たちが「オーリニャック文化期」と呼ぶ、クロマニヨン人が残した骨片から、この時代の人々が月の動きを記録していた可能性があるのだ。(ジュールズ・キャシュフォード『月の文化史』柊風舎、第1章参照)
もしこの仮説が本当なら、人類にとってもっとも初期の「暦」の記録となるだろう。
●月と暦、人間の意識とのかかわり
人類にとって最初の「暦」が月と密接に関係していたことは想像に難くない。
自然界のなかでもっとも規則的に変化し、そしてもっとも観測しやすいものといえば、月の満ち欠けに違いないからだ。
梅や桜の開花やウグイスの鳴き声は季節変化を風流に伝えるものではあるけれど、その数学的規則性という点では、月の満ち欠けには遠く及ばない。
それがごく最近まで月の満ち欠けを基にした太陰暦が世界中で用いられていた理由だろう。
そもそも、「ついたち」は「月がたつ」からきている。新月の光が現れることを意味するわけだ。
また英語の「カレンダー」も同じで、これはラテン語で、月が出たことを人々に呼び掛けることを意味するという。ローマではこの日に人々に給金が支払われたのだとか。
さらに、月を観測すること、そしてそこから暦を作ることが時間や人間の意識の発生そのものに深くかかわっていることは、英語のMoonという言葉の語源を考えるとよくわかる。いや、ぼくなど、それだけで戦慄のようなものを感じてしまうほどだ。
OED(オックスフォード英語辞典)などによると、Moonの語源はインドヨーロッパ語のmeとかかわりがあり、それは「測る」ということだという。
さらに、さきのキャシュフォード氏などによれば、それは英語のmental、mindなどともつながりを持つ。
つまりは、ぼくたちの、時間とそしておそらく空間を把握する精神構造の深層の基盤に、あのこうこうと輝く「月」が横たわっているのである。そして、それは占星術の起源でもあるといっていい。
●「100%自然」はあり得ない
ところで、最近、近代的な太陽暦にたいして太陰暦のほうが、ときには「マヤ暦」のほうが「自然のリズムに近い」ので、生活するに好ましい、などという主張を目にするけれど、それはぼくには理屈がまったくわからない。
天体の動きをみているとすぐにわかるはずだが、天体の運行は太陽や月も含めて、人間に都合良くどれも整数では割り切れないのである。カオス的運動をしているといってもいい。
人間にとって便利な「暦」はどんなものであれ、ありていにいってしまえば、整数によって、本来連続している自然の流れに文節を作り出すことによって完成する。
だからこそ、現在の暦でも、4年に一度は閏年をいれなければならないのだし、ときには閏秒をうれて修正することが必要になる。
また、月の満ち欠けによる暦は月のかたちと日付を合致させるという点でわかりやすいが、これだけを使うとあっという間に日付上の月日と季節がずれていってしまう。季節変化は太陽の運行に支配されているからだ。
中国起源の「二十四節気」(立春だとか啓蟄といったあれ)を導入したのは、この節気が太陽の動きを示すものであり、季節の指標としてどうしても必要だったからだ。
今の日本でこの節季の季節感がピンとこないのは、昔の暦と今の暦が違っているからではなく、節気が発明された中国内陸部の気候と日本の気候の違いを無視してそのまま導入してからにすぎないのだ。
どんな暦でも「100パーセント自然」などということはあり得ない。
そうではなく、自然と文化の接合面に生み出される、インターフェイスが暦だと考えるのが正解ではなかろうか。
そして、人間はそのときそのときに応じて、便利なそのインターフェイスを生み出すために血のにじむような努力を重ねてきたのである。
西洋占星術やインドの占星術は実際の天体の動きを用いている。中国の占いの多くはいったん、その天体の動きを「暦」のなかに落とし込み変換して占いに用いる。そこが東西の占星術の大きな違いだといえる。
拙携帯サイト「鏡リュウジ占星術」などでは、軌道計算によって惑星や太陽、月の動きを算出し、そのメッセージを伝えているのでぜひチェックしてみて欲しい。
また、今回のダイアリーはそうして計算した天体の運動を手帳に書き込んで、日々の生活に役立てて応用していただこうとしている。
このような「暦注」入りの暦は、英米ではアルマナックといわれ、17世紀のイギリスでは聖書と肩を並べるほどの売れ行きだったとか。
ぜひぜひ、お手許において、活用していただきたい。
(と、最後、宣伝で締めくくり失礼しました・・・)