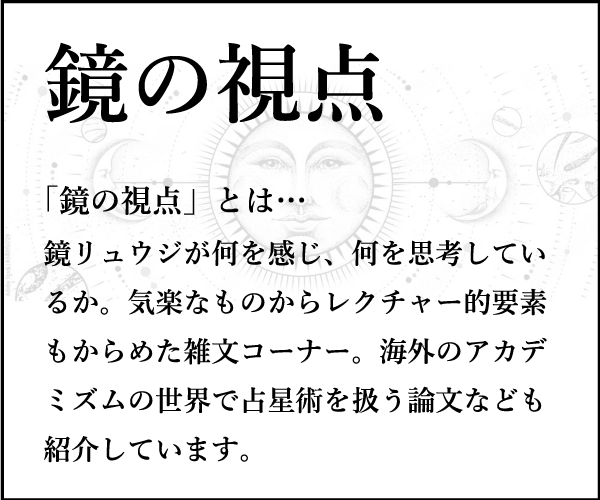贈り物の季節が今年もやってきた。イルミネーションがきらめいて、クリスマスソングが流れてくると、なんとなく気持ちがわくわくするのだ。プレゼントを選ぶのは、やっぱり楽しい。子供たちの笑顔を見るのも楽しいし、大切な人に、何がいいかとあれこれ迷いながらイメージを膨らませ、街を歩くのは贅沢な時間だといえる。
以前、「恋人がサンタクロース」なんて歌がヒットしたけれど、クリスマスシーズンはすべての人が「サンタクロース」になれるときなのではないだろうか。
いや、そんなことをいって単にいまの商業主義をロマンチックな言葉で飾り、推奨しようとしているつもりはない。
クリスマスの文化は資本主義とセットになっていることはよく知っているし、今の赤い服を着たサンタクロースは、実は某飲料メーカーのイメージ戦略によって定着したことも、当然知っている。
しかし、それでも、この「贈り物」ということを深く考えるときに、そこには魔法の力が確かに働いていること、そしてそれは占星術と根底でつながっていることが見えてくるのである。
たとえば、あなたが誰かへの贈り物を買いに行く時のことを考えてみてほしい。このクリスマスシーズンなら、レジで気のきいた店員なら「ご自宅用ですか、贈り物ですか」とちゃんと聞いてくれるだろう。そのとき、贈り物と答えたあなたに、店員はどういったサービスをしてくれるか。ラッピング? たしかにそうだ。しかし、それ以上に大事なことがある。
それは、値札を外す、ということ。
どんなに丁寧にラッピングしてくれても、もしその中に値札がついていたら、どんなに興ざめなことか。それがあとでわかったら、きっとあなたもクレームをつけたい気持ちになるに違いない。
しかし、考えてみればこれは不思議なことではないだろうか。これだけの情報化社会のことだ。たいていの商品の、だいたいの値段など、想像がつく。あえてブランド品を選んで、相手に値段を想像しやすくする、ということすら、ある種の戦略として用いられる場合もあるだろう。
だから、値段をわからなくするというような目的だとすれば、そこまでこだわる必要はない。しかし、値札を取り忘れた時に感じる「決まりの悪さ」はどうして起こるのだろうか。
値段ではなく、気持ちを贈るのだから・・・?
あなたはそう答えるかもしれない。では値段がついていたら、それは「気持ち」ではないのだろうか。
難しい問題だけれど、ぼくはこんなふうに考えるのだ。
値段が決まっているということ、あるいは値段をつけるということは、市場に出すことができる「商品」であるということだ。原理上、それは誰とでも売買が可能である。
しかも、見えない信用の上に成り立った貨幣によって価値を「等価」で交換する。そのときには、貸し借りはない。そのときの売買、交換では基本的には濃密な人間関係は発生しない。
100円のものなら、相手がだれであれ、いつであれ、100円支払えばそこで売買は完結する。そのかわり、そこには公平さや平等性を求めることができる。
コンビニのように極端にシステム化された店舗と、伝統的な地縁と結びついた商店との違いはここにある。等価交換というかたちではたやすく軽量化しにくいような「恩義」「貸し借り」「負い目」といったような勘定抜きに、便利に商いを成立させようとして、誰とでも、市場を拡大するべく成立したのが今の貨幣システムなのだから。
しかし、その一方で、そのような交換が人間関係を希薄化させてゆくこともよく指摘される。ファストフードチェーンが「スマイル0円」などとあえて、伝統的なサービスを演出しようとするのもここに秘密があるのではないだろうか。
値札を外すというのは、広く開かれた市場の商品ではなく、どこか別のところからやってきたモノであるということを表象する一種の儀式でもあるのだろう。
そう考えると、クリスマスプレゼントの古い歴史を想い起こさざるを得ない。
クリスマスにプレゼントをもってくる「サンタクロース」は何もキリスト教だけのものではない。
イギリスには、土星の神サトウルヌスをその前身とするファーザー・クリスマスがいる。フランスやスイスでは、女性の姿で表彰されるマダム・ノエルがいる。イタリアではなんと、魔女べファーナが子供たちにお菓子を運んでくるというのだ。
こうしたギフトギバーたちは、すべからく、異界からギフトを持ってくる。それは「買ってきた」ものではなく、ほかの世界からもたらされるものなのである。
クリスマスの起源は、これもよく知られているようにキリスト教起源ではない。聖書には12月25日がイエスの誕生日だなどとは書かれていない。クリスマスが12月に祝われるようになったのは実に4世紀に入ってからのことなのだ。
諸説はあるものの、多くの歴史家がいうにはもともとは冬至の祭りだったのである。昼が短くなり、夜がもっとも長くなるとき。太陽の信仰にもとづく、光の死と再生を祈念する祝祭が行われていた。
ローマで有名なのは、のちに皇帝崇拝とも結びつく「不滅の太陽」の祝祭で、これは12月25日だったという。こうした祝祭がキリスト教と混淆してクリスマスが成立してゆく。
そのときには「闇」の世界からさまざまな精霊や存在がやってきて、贈り物を与えるのだ。
ヨーロッパの冬は寒く長い。そのなかでは、人びとは温かな異界からの贈り物を待ち望み、日常の秩序の外にある恵みを期待し、感謝して受け取ったのだ。
いかに商業化されようが、「値札を外そう」という小さな気持ちの魔法が行われていることは、贈り物にはいまだに、異界からの恵みでありこの世のものではない、軽量化しにくい価値へと転換させようとする、古い古い意図がそこにこめられていることを示す。
昼間の計算とは異なる論理が、贈り物には働いている。闇のなか、無意識のなかからやってくる何かが贈り物には込められる。
その贈り物のロジックやしくみを基軸にした経済のありようもあるのではないか。それがたとえば一昔前に期待された地域通貨のようなものではないかと考えるのだけれど、どうなのだろう。
いずれにしても贈り物は素敵だ。昼の世界から解放されて、異界からの使者になるための魔法なのだから。